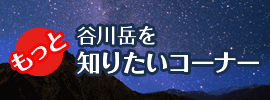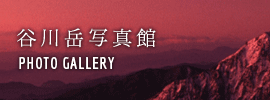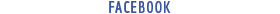落葉と紅葉
[落葉] ―落葉するのはなぜ?―
緑色植物は光合成を行い、自らの力で有機物をつくり生活をしています。秋に気温が下がり、根の働きも弱くなって水分の吸い上げが減ってきます。そこで、葉の気孔から水分が体外へ出ていくのを止めないと、植物は乾燥して枯れてしまいます。その為、落葉樹は葉を落すのです。(草本は果実を実らせた後、枯れる。)
植物にとっては、葉が開いて以来貯まっていた大気の汚染物質や、体内の老廃物を吐き出す良い機会となる。
落葉のメカニズム
乾期や厳寒期になり温度が下がると、根からの水分補給が減り、葉柄と茎との境に離層と呼ぶ小さな細胞の層ができる。この離層では、細胞壁の成分を溶かすセルラーゼ、ペクチナーゼなどと呼ぶ酵素がつくられ、この酵素の働きで細胞壁が溶けて弱くなると、維管束の木部も切れ、根からの水分の補給もなくなり葉が落ちる。
◆枯れた葉をつけたまま越冬=完全に離層がつくられない、離層ができ細胞間の分離が進んでも強靭な維管束でつながっている場合に起る。これらの植物は、本来、常緑性だったので、その性質を保持しながら温帯域まで分布を広げた。
ヤマナラシ(ヤナギ科)R291上の一~幽間に1本、カシワなど(ナラの仲間)
[紅葉] ―なぜ植物の葉は色ずくのか?―
紅葉のメカニズム
晴れた日が続くと、樹木は光合成を行い、デンプンを多量に蓄えます。温度が下がり根の働きも弱くなり水分の補給が減ると、葉柄基部に離層ができ、やがて葉柄の維管束の下面側にある蒒部の維管束が切れ、葉から茎への養分の移動が止まってしまう。
こうすると、デンプンは葉に貯まり糖に分解され、クロロフイル(葉緑素)は老化してアミノ酸に分解される。この時、急に低温になるほどクロロフイルの分解が促され、糖とアミノ酸が多くなる。そして、糖とアミノ酸によってアントシアン色素が合成される。
黄葉のメカニズム
葉にはカロチノイドという黄色の色素もあり、葉緑体では吸収しきれない光で光合成をしている。温度が下がりクロロフイル(葉緑素)が破壊されると、それまで隠れていたカロチノイドが表に出る。
褐葉のメカニズム
紅葉と同様な過程で、フロバフェン色素が合成される。 ブナが代表格。クリ、ケヤキなど。
[色づきの進む過程]
ハウチワカエデやメグスリノキなど=アントシアンが形成され、緑色から一時褐紫色
となり、クロロフイルが破壊されるに伴い、紅色味が増す。
イチョウの黄葉は葉の縁から中央に向って進行。進行途中→ 葉の中心が緑、縁が黄。
[様々な色づき]
同じ樹木でも、紅葉・黄葉・褐葉が見られる。葉にできた糖やアミノ酸の量、その他影響を及ぼす生理状態等で大きく変化する。
[春の紅葉]
新芽が赤で美しい。クロロフイルが合成される前のアントシアン色素の色。紫外線を防ぐのにアントシアン色素が有効。→エゾユズリハ、ベニカナメ、ヤマグルマなど
[季節はずれの色づき]
枝や葉が傷ついたり折れたり、虫害などに遭ったりして、葉柄や葉脈が切断されると、
糖類の移動が妨げられ、クロロフイルからアントシアン色素などに変化
[色づきの美しさ]
いかに多くのデンプンが葉に蓄えられたか+葉緑素がいかに早く分解されるかで決まる。それには、昼夜の温度差が大きいことも重要。
(夜の気温が高いと、昼に蓄えられたデンプンが呼吸に使われて減少する。)
[色づきの美しい種類]
鮮紅色=オオモミジ、ツリバナ、ドウダンツツジ、ナナカマド、コマユミ、ヌルデ、ハウチワカエデ、ヤマブドウ、ヤマウルシ等
暗紅色=イボタノキ、ガマズミ、ミズキ、ムラサキシキブ、ヤマザクラ、ヤマツツジ、
リョウブ、ヤマボウシ、レンゲツツジ等
黄色=イタヤカエデ、イチョウ、カツラ、カラマツ、シラカバ、ダンコウバイ、トチノ
キ、ホウノキ、マンサク、ヤマブキ等
黄色~茶色(褐色)=ブナ、クリ、ケヤキ、ミズナラ等
[針葉樹の葉色の変化]
冬に緑色が枯葉色に近く変色。気温の低下で水分吸収が低下し乾燥状態になり、葉の細胞内の細胞液が濃度を増し、同化作用も不十分になったところに日射により葉緑素の分解が進み、ロドキサンチンやカロチン色素が生じるため。春には元の緑色に戻る。
スギ、ヒノキ、マツ等
―モミジとカエデ―
[モミジとは]
色が揉み出すようにつく(動詞モミヅという古語)とか、紅色の布(紅絹地モミジ)とか、語源的には諸説あるが、要するに秋になって緑色の木の葉が変色すること全般を指した言葉で、赤く色づく紅葉と黄色や褐色に色づく黄葉とを合わせた意味。
尚、万葉集では多くの黄葉の字が当てられ、紅葉とあるのは少ない→唐などの影響と大和では紅葉より黄葉に親しんだ風土性。
※万葉集=4516首 うち動物名詠約1000首、植物名詠約1500首 うち黄葉88首 紅葉6首
[カエデとは]
万葉集では「蛙手」「加敝流手」の字が当てられ、葉形が蛙の手に似ていることに由来。カエデの種類 日本で27種(変・品種は54種)。中国が本場 130種
※モミジとカエデが同じ意味に用いられるようになったのは、モミジの中でカエデ類が色づきがよいからで、鎌倉時代以降。
※漢字で「楓」は誤り。中国中南部・台湾に分布するマンサク科の「フウ」のこと。
中国でカエデ類をさす感じは「槭」。
※モミジという言葉が他の植物の接頭語に用いられる場合=手のひら状に切れ込んだ葉の状態を表す意味に転じて、他の植物名に冠せられる。
→モミジイチゴ、モミジガサ、モミジカラマツ、モミジドコロ、モミジハグマ等
万葉集巻一 天智天皇に答えた額田王の長歌
冬ごもり 春さりくれば なかざりし 鳥もきなきぬ…秋山の この葉をみては 黄葉をば
枕草子一清少納言
かえでの木 ささやかなるにも もえ出てたる梢の赤みて 同じ方に さし広ごりたる